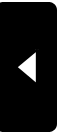2011年03月14日
震災に遭われた皆さんのご無事をお祈りしています
大変痛ましい震災が起こってしまいました。
現地の被害の様子、ここ松本からは報道と余震からうかがい知るばかりですが、
心が痛んで仕方がありません。
岩手と茨城には、これまでにキッチンを作らせていただいたご家族がお住まいです。
皆さんがご無事であることを祈るばかりです。
これまでにないことで、被害に遭われた皆さんの不安は想像に余りあります。
ただただ皆さんのご無事と、一日も早く安心できる日々が戻ってくることを祈っ
ています。
現地の被害の様子、ここ松本からは報道と余震からうかがい知るばかりですが、
心が痛んで仕方がありません。
岩手と茨城には、これまでにキッチンを作らせていただいたご家族がお住まいです。
皆さんがご無事であることを祈るばかりです。
これまでにないことで、被害に遭われた皆さんの不安は想像に余りあります。
ただただ皆さんのご無事と、一日も早く安心できる日々が戻ってくることを祈っ
ています。
Posted by ウラ夫 at
18:55
│Comments(0)
2011年03月11日
あなどれませんよ、カンボジアのクッキー
最近、落語を聴き始めました。
いきなり談志師匠の古い録音から入っちゃいましたが、
このリズムといい、間合いといい、これは音楽だわー!
と目下感動の日々を送っています、ウラ夫です。毎度どうも。
古典落語ですから、決まったテーマがありつつも、
師匠の生き生きとした噺しっぷりによって、いかようにも
輝きを変えるところなんざ、ジャズ、とりわけビバップの快演あたりを
聴いている感じでございます。
チャーリーパーカー独演会みたいなもんですね。
落語の中でも、特に「枕」から本題にすぅーっと入る瞬間が好きです。
ジャズでテーマリフを吹き終えて、粋なブレイクとともにアドリブに突入する、
いきなり談志師匠の古い録音から入っちゃいましたが、
このリズムといい、間合いといい、これは音楽だわー!
と目下感動の日々を送っています、ウラ夫です。毎度どうも。
古典落語ですから、決まったテーマがありつつも、
師匠の生き生きとした噺しっぷりによって、いかようにも
輝きを変えるところなんざ、ジャズ、とりわけビバップの快演あたりを
聴いている感じでございます。
チャーリーパーカー独演会みたいなもんですね。
落語の中でも、特に「枕」から本題にすぅーっと入る瞬間が好きです。
ジャズでテーマリフを吹き終えて、粋なブレイクとともにアドリブに突入する、
あの瞬間の見事さに通じるものがありますね。
と、σ(^^)もこんな枕からすぅーっと本題に入ろうと思いましたが、
あまりにムリヤリでダメですね…。
先日、ウラ夫の父がカンボジアを旅してきました。
悠々自適なおじさんは、世界を駆けめぐっています。
ハワイはともかく、中国に行けば紫禁城型チョコ、タイなら象さん型、
シンガポールならマーライオン型って、いくらチョコやクッキーが無難だからって、
それぞれの国のアイデンティティーはどうなのよ的なことはもちろん心に留め置いて、
チョコ好きなσ(^^)はポリポリやっていたわけです。
ご多分に漏れず、そのクッキーのうちのひとつはアンコールワット型でした。


と、σ(^^)もこんな枕からすぅーっと本題に入ろうと思いましたが、
あまりにムリヤリでダメですね…。
先日、ウラ夫の父がカンボジアを旅してきました。
悠々自適なおじさんは、世界を駆けめぐっています。
お土産に買ってきてくれたのが、なんとクッキー各種。
この頃は、まぁどこの国に行ってもマカデミアンナッツ入りのチョコレートかクッキーが
この頃は、まぁどこの国に行ってもマカデミアンナッツ入りのチョコレートかクッキーが
用意されているようで、旅の風情もないもんだなぁ、なんて、正直思ってました。
ハワイはともかく、中国に行けば紫禁城型チョコ、タイなら象さん型、
シンガポールならマーライオン型って、いくらチョコやクッキーが無難だからって、
それぞれの国のアイデンティティーはどうなのよ的なことはもちろん心に留め置いて、
チョコ好きなσ(^^)はポリポリやっていたわけです。
ご多分に漏れず、そのクッキーのうちのひとつはアンコールワット型でした。
しかし、ミルクなどほとんど飲まないであろう東南アジアでクッキーかよ…
なーんて思いながら一口食べてびっくり。これがなかなか美味しい。
なんというか、小麦粉・バター・卵など、まっとうな材料を惜しげなく使って、
すごーくまじめに作っている味。
工場ではなく、お母さんがていねいに手作りしたような、素朴で家庭的な味でした。
そしてもうひとつは、筒状に巻いた焼き菓子。
「ノム・トン・ムーン」て書いてあります。

これがまた美味しい!
こちらは薄い生地を折り畳んだものを筒状に巻いて焼いたようで、ほろほろと
くずれるほど、繊細な食感のクッキーです。
サクサクで上品な甘み。ふんわりココナッツの風味がして、カンボジアらしさを
感じることができます。
意外にもこれ、カンボジアの伝統菓子らしいです。
しゃれたお菓子があるものですねぇ。
さてさて、この2つのクッキー、美味しいだけでなく、意外な共通点がありました。
どちらも、日本人の方がカンボジアに渡って始められたご商売なのだそうです。
「アンコールクッキー」を作っているのは「マダムサチコ」の小島幸子さん。
「ノム・トン・ムーン」の方は「Cambodia Teatime」のモリシタヒデキさん。
経営は日本流にやりながらも、カンボジアの材料を使って、カンボジアの人たち
の手でていねいに作る。
お二人に共通するのは、カンボジアの人々や国を愛していて、事業を通して
この国にリアルな貢献をしていこうとされていることと感じました。
これらの事業により、現地の人々の雇用を生み、教育もされていることでしょう。
それにそれに、このクッキーの素朴なおいしさを通して、σ(^^)自身も
カンボジアについてより大きな興味を抱き始めました。
行ってみたいなー、かの国に。
以前、だまさん、なおー専務とタイに行った時には、現地、特にタイ北部の
伝統的なクラフトを、デザイナーが洗練した商品に仕立て上げた、タイ独自の
新しく魅力的なプロダクトにたくさん出会いました。
ここでも外国人によるプロデュースなどがきっかけとなって、タイ国内の伝統クラフトの
世界がしだいに活気づいてきているようなのです。
そういえば、この頃はタイ人のデザイナーも活躍していますしね。
カンボジアにしろ、タイにしろ、これから豊かになろう、発展していこう、という国は、
人も街もすごく元気です。
たとえ漠然としていたとしても、夢があるというか。
今の日本の子どもたちって、アホな夢を持てない子が多いのだそうです。
子どもたちが夢を自由に持てないのは、私たち大人が夢を語っていないからでしょうね。
大人も子どももなく、でっかい夢を口走りつつ生きたいものです!
というわけでカンボジア、近いうちに行っちゃう!と心に決めましたです。
ニッポンジンッテ、元気デアホナノネ~、と思ってもらえたらいいね~♪
と、まだ見ぬカンボジアに思いをはせつつ、ノム・トン・ムーンぽりぽり。
あー美味し。
2011年03月10日
妊娠中でも食べられる(かも?)料理・その1
パートナーのだまさんが、いよいよ妊娠5ヶ月目に入りました。

何せ、4ヶ月も間近で赤ちゃんができていることに気がついた(!)ので、
若干気持ちがついていけてない感があるウラ夫です。こんにちは。
この分じゃあ、ある朝起きたら産まれてました、みたいなことにはならないでしょうか!?
なりませんか、そうですか。
ところで5ヶ月目といえば、犬の日、じゃない戌の日ですよ。
「帯祝い」ともいうそうです。
神社などに行ってお詣りをし、帯みたいなものをまいて、
そのあとみんなでご馳走を食べる、という大体そんな感じの日です。
ウラ夫家では、二人目ということで若干余裕を見せ、
このうち、「お詣り」と「ご馳走を食べる」をチョイスしてみました。
帯祝いなのに、帯をまくのを省いてよいのか、という意見につきましては、
ちょっと聞こえなかったことにしておきます。
そんなわけで、なおー専務の時と同じ、松本の深志神社にお詣りをし、
I原良純さんもびっくり、リアルひげがもじゃもじゃの「松本だるま」を買いました。
本当はこのあと、松本が誇る美食処、ヒカリヤさんでおご馳走をいただこうと
計画していたのですが、だまさんのつわりが未だ収まらないので、惜しみつつも
今回は断念したのです。
今回のだまさんのつわりは、ネギニンニクの類を筆頭に、魚介類、挽き肉がダメ。
調味料も、しょう油・カツオだしが全面的にNGという、どう転んでも和食には
ありつけないという環境。
こんな過酷な条件の中、臨時主夫ウラ夫は、今日もがんばって料理に
励んでいるわけであります。
この条件を満たした上で、滋養があり、かつ、このつわりの姉さんに
少しでも美味しく食べてもらえる料理を考える、というのは、なかなかちょっとした
パズルを解くような感じで、挑戦のしがいもあるっつうもんです。
よっ、前向キング・ウラ夫さん♪
いつもながら枕が長くてすみません。
そんな中で作った、思いつき料理の中から、だまさんに割と好評だった料理を
書いてみます。
「鶏肉と大根のサムゲタン風麦スープ」

えーと、最初に断っておきますが、上の画像は本物のサムゲタンです。
できあがりの見た目が似てたので引っ張ってきちゃいました。
実はこのブログを書く前に食べちゃった!のでした…。
もちろん今回ネギなしでね。ネギを載せたら確実にひっぱたかれます!
<材料>
・鶏肉(骨付き) 食べたいだけ
・大根 鶏肉と同じぐらい
・押し麦 ひと握り
・チキンだし
・しょうが 少し
・クコ(あれば) 少し
・香菜(あれば) 少し
※基本的に分量はテキトーです。
<作り方>
・圧力鍋に、鶏肉丸ごとと、しょうがのスライス、水(チキンだし)を入れて煮ます。
・アクをとったら、ごろごろっと切った大根と押し麦をひとつかみ投入。
・フタをして鶏肉がやわらかくなるまで煮ます。
・煮えたら塩などして完成。(妊婦にばれない程度にしょう油を入れても可)
・香菜(パクチー)とクコを散らすと更に美しく、おいしいですよ。
とまぁ、わざわざ書くほどでもないほど簡単です。
ひとつ大事といえば、鶏肉はなるべく良いものを使いましょうね。
鶏肉と麦からでたとろみが良い感じ。
スプーンの先でほぐれるほどやわらかくなった鶏肉のうまみが大根にしみて、
簡単な割に、なかなか滋味あふれる一品でございますですよ。
ちなみにウラ夫はこの「滋味」ってことばが大好きです。
あったまるし、おなかには優しいし、うちの妊婦さんにも食べられました!
ウラ夫家では、寒い冬の日、風邪をひいた時なんかにも、これを作ります。
妊婦さんがいてもいなくても、ひとつお試しを。
2011年03月08日
キッチンつくるなら、ガス?それともIH?(後編)
えーと、そうそう、ガスかIHかという話です。
昨日はすっかり話がそれてしまいました。(前編を読んでいない方はこちら)
そうは言っても、IHのことで一番ご質問を受けるのが、この電磁波の話なので、
まあよかったんだ、ということにしましょう。
昨日はすっかり話がそれてしまいました。(前編を読んでいない方はこちら)
そうは言っても、IHのことで一番ご質問を受けるのが、この電磁波の話なので、
まあよかったんだ、ということにしましょう。
前向キングのウラ夫です。こんにちは。
さて、ウラ夫家のキッチンはガスコンロです。
家を建て替えたことがないので、IHに換える機会がなかったんだとも言えますが。
個人的には裸火の見えるガスコンロが好きです。
火が見えないと、料理をしている気になれないし、
冬の夜など、お茶でも入れようとコンロに火がともると、
さて、ウラ夫家のキッチンはガスコンロです。
家を建て替えたことがないので、IHに換える機会がなかったんだとも言えますが。
個人的には裸火の見えるガスコンロが好きです。
火が見えないと、料理をしている気になれないし、
冬の夜など、お茶でも入れようとコンロに火がともると、
それだけで部屋の空気が人気づくというか、暖まる気がします。
あと、子どもにはキッチンで、火の楽しさと怖さを学んでほしい、という気持ちもあるんです。
実は先日、長年使っていたガスコンロの調子がいよいよ悪くなり、
実は先日、長年使っていたガスコンロの調子がいよいよ悪くなり、
新しいコンロに買い換えたんですが、これが思わぬ不満・不便をもたらしました!
ここ1,2年でコンロを買われた方はご存じかと思いますが、
現在市販されているコンロには、Siセンサーという温度センサーがついています。
バーナーの真ん中のところ。
鍋を置くと沈むようになっているボタン形のものがそうです。
火のつけ忘れや、天ぷら油の過熱など、ガスコンロが原因となる火災を防ぐために、
約250℃で自動消火する機能です。
また、センサーの上に鍋が載っていない場合も、自動的に火が小さくなったり消えたりします。
便利で安全~♪ということなのですが、実はこれがやっかいなのです。
例えば、中華鍋で炒め物。
焦げ付かないように、短時間で美味しく炒めるには、煙が立つほど鍋を熱してから
調理するのがキホンなのですが、
これをすると、コンロが空焚きと判断して、勝手に火を弱めてしまいます。
また、同じく中華鍋を持ち上げて鍋を振る、あるいは、コンロに直接のせないで、
海苔などをあぶる場合。
やはり、鍋が載っていないと判断して、火を小さくしてしまいます。
他にも、焼き網が使えないので、魚、お餅などを網焼きすることが出来ません。
パンを網で焼くと短時間でカリッと焼けるので気に入っていたのですが、
これも出来なくなりました。
なんだか、これまで出来てあたりまえだった、料理のキホン動作が出来なくなって、
とっても窮屈な思いをしています。
実は上のような使い方をする時のためにと、「センサー解除ボタン」なるものが
ついているんですが、これは、実は消火する上限温度を250℃から290℃に
上げるだけであって、「センサーが解除」されるわけではありません。
(まぎらわしい呼び名です!)
したがって、このボタンを押しても、上記の料理動作ができないことには変わりありません。
この間など、どうしても網で肉を焼きたくて、一方のバーナーで焼きはじめたところ、
すぐに火が弱まるので、すかさず隣のバーナーに移動。
しかし、そのバーナーもすぐにセンサーが働くので、また元のバーナーへ移動。
(この時、一度火を消して、つけ直す。) 火が弱まったらまた隣へ…この繰り返し。
ちなみに網がセンサーに触れると火が消えてしまうので、この間ずっと、
網をコンロから少~し浮かせて火にあぶるようにする必要があります。
想像してみて下さいね。 右、左、みぎっ、ひだりっ…。
まるで注文殺到で焦りに焦る、手焼きせんべい屋のような、なんとも情けない光景でした。
最近は土鍋でご飯を炊くのにハマって、炊飯器を処分してしまったんですが、
新しいコンロに火をかけておくと、強火にかけていたはずが、気がつくと勝手に弱火になって
いたりすることもあって、慌てさせられます。
このセンサー、現在市販されている全てのガスコンロについています。
2008年にできた法律で、このセンサーがついていないと販売も設置もしてはいけない
ことになりました。
これによって火災が劇的に減るのだとしたら、歓迎もできるのですが、
料理をする側からすると、あたりまえのことが出来なくなるのはすごく不便だし、とまどいます。
そして、もうひとつの問題は、海外メーカーのコンロが使えなくなること。
この法律は日本だけのものですから、海外のメーカーには、このセンサーをつける動きは
ほとんどありません。なので、輸入コンロは現在、実質使用禁止となっています。
人気のあったロジェールも、ガゲナウも、マジックシェフも…。使えません。
インテリア雑誌などに載っているオシャレなキッチンには、たいがい輸入コンロが
入っていたものです。
今でもそういった雑誌をお持ちになって、こんなスマートなコンロにしたい、
と希望されるお客さまがいらっしゃいます。 が、残念ながら、今は無理なのですよ~…。
国内3社(リンナイ・ハーマン・パロマ)から選んで頂くほかないのです。
この法律、実はガス業界が自主規制のために作ったのだそうで。
だけど、どうなんでしょう。使い勝手は悪くなるわ、スマートな海外製品は選べなくなるわで、
こんなんだったら、この機会にIHにしちゃおう、という方も多いのではないでしょうか。
電力会社や家電メーカーもIHの売り込みにがんばっているし、
見た目スッキリ、という面ではどうしてもIHの方が有利だし。
これじゃ多くの人がIHに流れてしまう、というのがわからないんでしょうかね。
IH普及のために、巷ではよく、「IHで出来るお料理教室」みたいなイベントを見かけます。
これで、IH初体験の人々が、「IHって思ったより便利なのね~」とIH派になっていくのでしょう。
どちらがよいかは好みの問題ですが、裸火が見たいσ(^^)としては、逆に、
「ガスでしかできないお料理教室!」なんてのやって巻き返そうよ~、と思うんですけどね。
どうなのよ、ガス業界さん。
でもな~、あぶれない、網使えない、空焼きできないんじゃ、
ガスコンロのメリット、全くうたえないですよね。
さみしいな~、と思う、裸火派のウラ夫なのでした。
2011年03月07日
キッチンつくるなら、ガス?それともIH?(前編)
朝起きたら松本は大雪でした。
昨日、「この辺りは3月でも雪降るの~?」と、
東京のTさん(穂高に新築中)に尋ねられたので、
「3月の雪は間違いなく大雪ですよ~!」と、
若干おどかしてさしあげたわけですが、まさか翌日にこうなるとは…。
最近予言が好調なウラ夫です。こんにちは。
今日は穂高の現場に向かわれるとか。大丈夫かな~?
Tさんはお医者さんでもあって、IH調理機器が発する電磁波の安全性について
強い関心を持っておられました。
σ(^^)もこの問題には興味があって、定期的かつ一生懸命に調べ上げるのですが、
安全・危険双方の意見があって、なんとも結論づけにくい。
現在、σ(^^)がとらえている事実は、こうです。
「(危険か安全か)今のところわかっていません。わかるように、より研究が必要です。」
ずいぶん雑な話と感じられるかも知れませんが、これが今の事実です。
そもそも電磁波が人体にどういった影響があるのか、これがはっきりとはわかっていません。
ですが、悪影響がある可能性も否定できないため、機器メーカーや関連団体などは
それぞれに安全基準を設けて、機器づくりをしています。
ですが、危険性の度合いが把握されていない以上、この基準が正しいのかどうかも?です。
よく言われる、ヨーロッパではIHがほとんど普及していない、という話は今は昔の感がありますし、
ヨーロッパの製品の方が基準が高いので安全、という話も、あまり鵜呑みには出来ません。
こうなると、あとは使う側の私たちが、未知の危険性に対してどう考えるのか、
ということになってきます。
危うきは避けるべきか、便利さなどの今現在のメリットを享受するか。
新しいものには、多かれ少なかれつきまとう問題ですね…。
えーと、実は今回はこのことを書きたかったわけではないのですよ~。
でも、IHと電磁波のことって、多くの方にとって関心の高い話かも知れませんね。
このことについては長くなるので、またゆっくり書きたいと思います。
というわけで、タイトルと違う方向に話が行きました。
個人的にガス派かIH派かと聞かれれば、ウラ夫家はガスなんですが、
料理に割と熱を傾ける者としては、今日日のガスコンロには文句があるゾ!
というのが、今回のテーマだったのですよ。
というわけで、乱暴にも次回に続きます。
すみませーん!
2011年03月04日
学習机、どうしてますか?(後編)
ウラ夫です。こんにちは。
昨日の続きです。
ちょうど1年前の3月に、「子どもを育てる、木の学習机展」というのをやりました。
この展示の期間中、来場していただいた皆さんに、学習机にまつわる思い出や、
今はどんな机をお子さんたちに与えたいと思っているか?
また、子どもたちには、学習机についてどう思っているか?
即席のアンケートに協力していただきました。
↑拡大すると結構読めます。
・小3の時にやっと買ってもらったのに、そこで勉強した記憶はほとんどなく…(30代・女性)
・自分の城ができてうれしかった。(30代・女性)
・冷たくサビの浮いたスチール製の学習机。何でこんなもの買ったんだ、と…(30代・女性)
・独りぼっちでさみしかった…かも。(30代・女性)
・キャラクターの机がよかった!と言われた…
・好きなものを並べて楽しんだ記憶があります。(20代・女性)
・学習机いらない!(12歳・男子)
・リビングで勉強した方が成績が上がるんですって…(50代・女性他)
・引き出しがほしい!早く、机ほしい!(4歳・女子)
・捨てられたり、放置されるのは惜しい(60代・男性)
・机でよく寝てた。(37歳・女性)
・広すぎて、本が山積みになってた。(36歳・男性)
その他にもいろいろ。面白いですね。
極めつけはこれ。
ある中学生の男の子に聞いてみた。
「学習机さぁ、どんな風に使ってるの?」
「あー、引き出し?要らないものを入れてるよ!」
「…」
一応見ときますか。

「……」
σ(^^)の中でのちょっとした結論。
こどもたちは、大人が思うように、期待するようには使ってくれないもの。
というか、こどもたちは自分の居心地のいい場所に、思い思いに自分の巣を
作るものなんだ、とあらためて実感。
それが机であったり、そうでなかったり。
もちろん、机が自分のお気に入りの場所になって、勉強だけではなく、
そこで整理整頓をおぼえたり、自分だけのヒミツができたり、
工作やお絵かきに没頭する楽しみを見つけたりすることもありますよね。
こどもたちにとって学習机は、初めて与えられた、自分だけの世界への入り口
なのかも知れません。
ちなみにσ(^^)は小学生の頃、自分の机に向かうと、ひたすら漫画を描いたり
発明活動(ほぼ妄想)に没頭していました。
というわけで、市販の学習机。
この引き出しにはA4ファイルがぴったり納まりますよ~、とか
ここはペン立て、この棚には教科書が並びますよ~、とか
デザイナーはいろいろと工夫して考えるわけですが、
こどもたちは常に一枚上手ってわけなのですよねー。
キッチンをつくる時と同じように、子どもたちの夢や希望をとことん聴いて、
一緒にワクワクしながら、ひとり一人にふさわしい机や家具が作ってあげられたら
いいよなぁ、なんて思うんです。
こどもたちのための家具づくりは、楽しいですからねー♪
2011年03月03日
学習机、どうしてますか?(前編)
3月になりました。
こどもは進級・進学に、おとーさんは税金の支払いに、
うんとワクワクする季節です。
ウラ夫です。こんにちは。
この時期になると、学習机の問い合わせをいただくことが多くなります。
キッチンだけでなく、お子さんの家具などもいろいろとオーダーで
作らせていただいています。
ところで、この学習机については以前からいろいろと疑問がありました。
今は家具屋さんに行っても、昔流行ったようなアニメキャラクター満載の
スチール机はほとんど見かけません。
代わって主流なのは、木目調で割と落ち着いた感じの学習机。
中には、こども社長のデスクか?と思わせるようなシブい路線のものも。
親としては、せっかく買うなら大人になっても使えるものを、と
比較的シンプルなものを選ばれる方が多いようです。
中学生ぐらいになった頃に、急にキャラクター机が恥ずかしくなってしまった、
そんな自分たちのこども時代を思い出しているのかも。
まあ、それはそれなんですが、
当のこどもたちが、初めて買ってもらった自分の机、
しかも自分のお気に入りのキャラ付き!の嬉しさに心躍らせる気持ちも
わかる気がします。
小学1年生が、あまりにシブくて立派な大人机に向かうのも、
なんだか無理がある気がしますし…。
じゃあ、もっと後になってから買えばいいのかな?
どうせ、小学校のうちは「机で学習」なんてしないよな~
(親本人が経験上よーく知っている…)
そもそも子どもに「学習机」って本当に必要なのかな?
ひょっとして、みんな似たような疑問を持っているんではないかしら、
と思い、ちょうど1年前の3月、「子どもを育てる木の学習机展」という
企画展を開催しました。
その時の様子↓

さてさて、この展示の期間中、来場していただいた皆さんに、学習机の思い出や、
こどもは進級・進学に、おとーさんは税金の支払いに、
うんとワクワクする季節です。
ウラ夫です。こんにちは。
この時期になると、学習机の問い合わせをいただくことが多くなります。
キッチンだけでなく、お子さんの家具などもいろいろとオーダーで
作らせていただいています。
ところで、この学習机については以前からいろいろと疑問がありました。
今は家具屋さんに行っても、昔流行ったようなアニメキャラクター満載の
スチール机はほとんど見かけません。
代わって主流なのは、木目調で割と落ち着いた感じの学習机。
中には、こども社長のデスクか?と思わせるようなシブい路線のものも。
親としては、せっかく買うなら大人になっても使えるものを、と
比較的シンプルなものを選ばれる方が多いようです。
中学生ぐらいになった頃に、急にキャラクター机が恥ずかしくなってしまった、
そんな自分たちのこども時代を思い出しているのかも。
まあ、それはそれなんですが、
当のこどもたちが、初めて買ってもらった自分の机、
しかも自分のお気に入りのキャラ付き!の嬉しさに心躍らせる気持ちも
わかる気がします。
小学1年生が、あまりにシブくて立派な大人机に向かうのも、
なんだか無理がある気がしますし…。
じゃあ、もっと後になってから買えばいいのかな?
どうせ、小学校のうちは「机で学習」なんてしないよな~
(親本人が経験上よーく知っている…)
そもそも子どもに「学習机」って本当に必要なのかな?
ひょっとして、みんな似たような疑問を持っているんではないかしら、
と思い、ちょうど1年前の3月、「子どもを育てる木の学習机展」という
企画展を開催しました。
その時の様子↓
これは、1年生になる女の子のために作ったもの。
キャラ付きではないけれど、あんまり大人びてしまうのも残念。
やっぱり子どものうちは、かわいくて、机に向かうことにウキウキすることだって大事!
と思うわけです。
そして将来、大きくなったら、机とキャビネットはそれぞれ独立して別々に使うことが
出来るようになっています。
こちらはσ(^^)からの提案。
家族が集まる部屋の真ん中に置きます。
子どもが家族から離れて独りで机に向かうのではなくて、親子が一緒の机に
向き合いつつも、それぞれが勉強なり家事なりに向かえたらどうかな、と。
ダイニングで勉強する子どもが意外に多いことから、本当は子どもたち、
家族の輪から離れるのさみしいんじゃないかな、と思ったんです。
向き合いつつも、それぞれが勉強なり家事なりに向かえたらどうかな、と。
ダイニングで勉強する子どもが意外に多いことから、本当は子どもたち、
家族の輪から離れるのさみしいんじゃないかな、と思ったんです。
さてさて、この展示の期間中、来場していただいた皆さんに、学習机の思い出や、
お子さんにどんな机を与えたいかなど、即席のアンケートに協力していただいたのですが、
これが何とも面白かったんです。
長くなりましたので、勝手に明日に続きますよ~。
2011年03月01日
オルガンジャズ・ライブのお知らせ
ウラ夫です。こんにちは。
キッチンづくりのかたわら、ジャズオルガンとピアノを弾いていますが、
久々にライブをすることになりました。
気が付くと、なんと今年初めてです。長めの冬眠でございました~。
ジャズオルガンって何?という方のために簡単にご説明しますね。
σ(^^)の弾いているオルガンはハモンドオルガンといいます。
小学校の教室にあったようなオルガンとはちょっと雰囲気が違います。
↓こんな感じ。

キッチンづくりのかたわら、ジャズオルガンとピアノを弾いていますが、
久々にライブをすることになりました。
気が付くと、なんと今年初めてです。長めの冬眠でございました~。
ジャズオルガンって何?という方のために簡単にご説明しますね。
σ(^^)の弾いているオルガンはハモンドオルガンといいます。
小学校の教室にあったようなオルガンとはちょっと雰囲気が違います。
↓こんな感じ。

今から約80年ほど前のアメリカで発明された楽器で、その当時、パイプオルガンなど
買えなかった黒人たちの教会などに、その代用品として取り入れられていきました。
そんな中からゴスペルやジャズ、ブルースなどが花開いていったわけですね。
電気楽器のはしりとも言えるもので、中にはたくさんの真空管と、歯車がシュルシュルと
買えなかった黒人たちの教会などに、その代用品として取り入れられていきました。
そんな中からゴスペルやジャズ、ブルースなどが花開いていったわけですね。
電気楽器のはしりとも言えるもので、中にはたくさんの真空管と、歯車がシュルシュルと
回っている、今となっては外見・音ともに、実にレトロでよい雰囲気をたたえた楽器です。
ご覧のように、家具屋の目から見ても大変美しい楽器なのであります。
このハモンドオルガン、アメリカでは今でも盛んに聴かれる楽器ですが、
ご覧のように、家具屋の目から見ても大変美しい楽器なのであります。
このハモンドオルガン、アメリカでは今でも盛んに聴かれる楽器ですが、
なぜかこの日本では他の楽器に比べてあまりよく知られていません。
ピアノと違って、オルガン自体があまりないため、実際の演奏に触れられる機会も
ピアノと違って、オルガン自体があまりないため、実際の演奏に触れられる機会も
とても少ないのではないかと思います。
しかし、一度聴いていただければわかりますが、独特のあたたかさと繊細さ、
しかし、一度聴いていただければわかりますが、独特のあたたかさと繊細さ、
そして華やかさを持った、とっても魅力的な音楽を奏でることが出来るんです。
σ(^^)の心の師匠、河合代介さんのソロ演奏をどうぞ
というわけで、そんなハモンドオルガン、とりわけオルガンジャズに触れていただく機会を
微力ながらつくりたい、とσ(^^)も時々演奏をしています。
このブログでも、ライブスケジュールをお知らせしていきますので、
ご興味のある方、ぜひとも一度お運び下さいませませ。
4月9日(土)19:30~ ファイブペニーズ(岡谷市)
σ(^^)の心の師匠、河合代介さんのソロ演奏をどうぞ
というわけで、そんなハモンドオルガン、とりわけオルガンジャズに触れていただく機会を
微力ながらつくりたい、とσ(^^)も時々演奏をしています。
このブログでも、ライブスケジュールをお知らせしていきますので、
ご興味のある方、ぜひとも一度お運び下さいませませ。
4月9日(土)19:30~ ファイブペニーズ(岡谷市)
Lazy Khan(レイジーハーン)、他1ユニット
浦野伸也 ;Hammond organ
小倉洋平 ;alto sax.
宮島弘樹 :guitar
中野耕二 ;drums
ちなみに、6月にはさるプロボーカリスト、ジャズ界の重鎮プレイヤー他を、
この松本にお招きしてのライブも予定しています。
σ(^^)も胸を借りるつもりでがんばりますよ♪
詳細が決まりましたら、またお知らせします。
2011年02月28日
キッチンに木の天板は向かない?
ウラ夫です。
先週末、5年前にキッチンを作らせていただいたSさんのお宅に伺いました。
久々にキッチンとご対面~♪

(画像は完成当時のものです)
Sさん家のキッチンは木の天板。サクラの無垢材です。
「全然手入れが行き届いてなくて~」
そう言うSさんですが、とても5年以上立つとは思えない美しさ。
あたたかな紅色にやけて、家の雰囲気にすっかりとけ込んでいました。
多くの方が、キッチンに木の天板~?
水や火に弱いんじゃない?汚れやすいんじゃない?
そんな風に心配をされます。
Sさんもキッチンを作る時、同じように迷われていた方のひとりでした。
木のワークトップにしたい気持ちはあるのだけれど、
汚れやすいのではないかと心配で、決めかねていたのだそう。
なんでも、参考にと見せてもらったお知り合いの木のキッチンが、
かなりエラいことになっていたとか…。
そんな状態を見て、やっぱり木の天板は無理なのかなぁ、と考えていたのだそうです。
一般的には、木は水や火に弱いもの、と思われていることが多いようです。
が、適切な使い方とお手入れがされていれば、決してそんなことはありません。
・水などをこぼしたら、こぼしっぱなしにしないで拭いてあげる。
・熱い鍋などを直接置かない。
・時々蜜ロウワックスを塗ってあげる。
基本的には気をつけるのはこれだけです。
ひとつひとつは何てことはない、あたりまえのことですよね。
キッチンは毎日使う道具ですから、毎日使えばキズもつきますし、
時にはシミや痕もつくでしょう。
でも、それもいいじゃない!と思うんです。
毎日の生活の中でつく、ちょっとしたキズや痕。
日に日に少しずつやけて変わっていく色味。
フキフキお手入れするほどに増していくツヤ。
新品の時には決して得られない、何とも言えない味わいが育ってきます。
家族と一緒に育っていくキッチンなんて素敵じゃないですか♪
まして、σ(^^)の作るキッチンでは、天板にもウレタンなどのニス類は塗りません。
ふつうは防水・防汚のために塗膜をかけるんですよね。
しかし、ママルでは使い始めて数年の美しさ・手入れのしやすさだけではなくて、
10年20年先に向かってどんどん美しくなっていくことを考えて、
蜜ロウワックスだけで仕上げることにしています。
こまめに乾拭きをし、蜜ロウを塗ってあげるだけで、水もはじきますし、
汚れもつきにくくなります。
木の表面がかさついてきたら、水はじきが悪くなってきたら、ワックスを塗ってあげる。
お肌の乾燥に、ハンドクリームなんかでうるおいを与えてあげるのと同じ。
木の表面がまたみずみずしく、生き生きとしてきます。
木が喜んでいるのがわかって楽しいですよ~。
その後、Sさんと一緒に、木のキッチンを10年来使われている家具職人さんの
ご自宅を訪ねました。
前述のあたりまえのこと以外、特別なことはしていない、というその天板も、
とても自然な風合いで、よい年のとり方をしていました。
これを見て安心し、Sさんはキッチンの天板を木にすることを決心したのでした。
そしてあれから5年。
キッチン完成と同時に生まれたSさんの娘さんはもう5歳。
キッチンと同い年なのね~。
なんとも感慨深いものがあります。
ちなみに、今回お訪ねしたのはキッチンではなく、お子さんの部屋にしつらえる
家具の打ち合わせ。
ところが、上のお兄ちゃんのリードにより、なぜかWii大会へ突入。
そのあともSさん家族みんなでトランプしたりはしゃいだり。
えーと、打ち合わせは… まいっか~!
ということで、すっかり子どもたちと遊びまくってテンション高く、
そしてふらふらになって、Sさん宅をあとにしました…。
なんというか、キッチンのご相談をきっかけに出会ったご家族と、
こんな風に何年たっても親しいおつきあいをさせていただけることが、
何ともうれしいんです。
この仕事をしていてよかった、ありがたいなぁと思う瞬間です。
Sさん、心配しないで。
お子さんの家具をデザインするためには、こうして彼らとしっちゃかめっちゃかになって
遊ぶことにも意味があるのですよ、きっと。
お子さんたちの夢やヒミツがたくさん納まる家具を作りますね~♪
先週末、5年前にキッチンを作らせていただいたSさんのお宅に伺いました。
久々にキッチンとご対面~♪

(画像は完成当時のものです)
Sさん家のキッチンは木の天板。サクラの無垢材です。
「全然手入れが行き届いてなくて~」
そう言うSさんですが、とても5年以上立つとは思えない美しさ。
あたたかな紅色にやけて、家の雰囲気にすっかりとけ込んでいました。
多くの方が、キッチンに木の天板~?
水や火に弱いんじゃない?汚れやすいんじゃない?
そんな風に心配をされます。
Sさんもキッチンを作る時、同じように迷われていた方のひとりでした。
木のワークトップにしたい気持ちはあるのだけれど、
汚れやすいのではないかと心配で、決めかねていたのだそう。
なんでも、参考にと見せてもらったお知り合いの木のキッチンが、
かなりエラいことになっていたとか…。
そんな状態を見て、やっぱり木の天板は無理なのかなぁ、と考えていたのだそうです。
一般的には、木は水や火に弱いもの、と思われていることが多いようです。
が、適切な使い方とお手入れがされていれば、決してそんなことはありません。
・水などをこぼしたら、こぼしっぱなしにしないで拭いてあげる。
・熱い鍋などを直接置かない。
・時々蜜ロウワックスを塗ってあげる。
基本的には気をつけるのはこれだけです。
ひとつひとつは何てことはない、あたりまえのことですよね。
キッチンは毎日使う道具ですから、毎日使えばキズもつきますし、
時にはシミや痕もつくでしょう。
でも、それもいいじゃない!と思うんです。
毎日の生活の中でつく、ちょっとしたキズや痕。
日に日に少しずつやけて変わっていく色味。
フキフキお手入れするほどに増していくツヤ。
新品の時には決して得られない、何とも言えない味わいが育ってきます。
家族と一緒に育っていくキッチンなんて素敵じゃないですか♪
まして、σ(^^)の作るキッチンでは、天板にもウレタンなどのニス類は塗りません。
ふつうは防水・防汚のために塗膜をかけるんですよね。
しかし、ママルでは使い始めて数年の美しさ・手入れのしやすさだけではなくて、
10年20年先に向かってどんどん美しくなっていくことを考えて、
蜜ロウワックスだけで仕上げることにしています。
こまめに乾拭きをし、蜜ロウを塗ってあげるだけで、水もはじきますし、
汚れもつきにくくなります。
木の表面がかさついてきたら、水はじきが悪くなってきたら、ワックスを塗ってあげる。
お肌の乾燥に、ハンドクリームなんかでうるおいを与えてあげるのと同じ。
木の表面がまたみずみずしく、生き生きとしてきます。
木が喜んでいるのがわかって楽しいですよ~。
その後、Sさんと一緒に、木のキッチンを10年来使われている家具職人さんの
ご自宅を訪ねました。
前述のあたりまえのこと以外、特別なことはしていない、というその天板も、
とても自然な風合いで、よい年のとり方をしていました。
これを見て安心し、Sさんはキッチンの天板を木にすることを決心したのでした。
そしてあれから5年。
キッチン完成と同時に生まれたSさんの娘さんはもう5歳。
キッチンと同い年なのね~。
なんとも感慨深いものがあります。
ちなみに、今回お訪ねしたのはキッチンではなく、お子さんの部屋にしつらえる
家具の打ち合わせ。
ところが、上のお兄ちゃんのリードにより、なぜかWii大会へ突入。
そのあともSさん家族みんなでトランプしたりはしゃいだり。
えーと、打ち合わせは… まいっか~!
ということで、すっかり子どもたちと遊びまくってテンション高く、
そしてふらふらになって、Sさん宅をあとにしました…。
なんというか、キッチンのご相談をきっかけに出会ったご家族と、
こんな風に何年たっても親しいおつきあいをさせていただけることが、
何ともうれしいんです。
この仕事をしていてよかった、ありがたいなぁと思う瞬間です。
Sさん、心配しないで。
お子さんの家具をデザインするためには、こうして彼らとしっちゃかめっちゃかになって
遊ぶことにも意味があるのですよ、きっと。
お子さんたちの夢やヒミツがたくさん納まる家具を作りますね~♪
2011年02月23日
「ロバの音楽座」のコンサートに行って来ました
ウラ夫です。こんにちは。
先週末、なおー専務(3歳)と軽井沢へお出かけしてきました。
「ロバの音楽座」のコンサートを観るためです。
「ロバの音楽座」は一見して中世ヨーロッパの古楽合奏団の風情で、
全国の子どもたちのために、音楽の楽しさを届ける行脚をされている皆さんです。
σ(^^)が音楽座のことを知ったのはもうかれこれ15年以上前のこと。
当時買った某建築雑誌に載っていた、音楽座の劇場兼けいこ場の建物(ロバハウス)の写真を見たのがはじまりです。
それこそ中世ヨーロッパの民家を思わせるような、土くれのような小屋(失礼)に、
目が釘付けになりました。
木と土だけで出来ているかのような風体。壁と天井は珪藻土であなぐらのように
塗り込められていて、そこにリュートやバグパイプなど、様々な古楽器が並べら
れていました。いい音響きそう。
中学生の頃から民族音楽マニアへの道を踏み出していたウラ夫さんです。
当時作っていた家具のテイストも、すっかりそっち方面に傾倒することとなりました…
それはともかく~。
当時からすごーく興味があったのですが、彼らの音に出会うのはこれが初めてでした。タブラトゥーラのような音楽かな?などと期待しながら…。
今回、軽井沢で野外保育園をされている方々が中心となって企画されたようで、
会場にはたくさんの子どもたち、お母さんたちがワイワイと集まっていました。
普段まずじっとしていられないなおー専務でも、これなら安心。
ところが、演奏が始まった途端、それまでガヤガヤしていた子どもたちが、
ひとり残らず静まりかえり、眼は音楽座の皆さんに釘付けになりました。
3~6歳くらいの自由な年頃の子どもたちが多かったようですが、全員が
一瞬で彼らの不思議な音の世界に引き込まれていきました。
あの様子、子どもたちの表情、もう感動的でした。
「さぁ、耳をすましてごらん」
いろいろな古楽器の、小さいけれどもそこでやさしく鳴っている感じの音に、
4人の風のようなうた声。空気が音でふんわかとあたたまるのがわかりました。
音をことばにするのは野暮かと思うのでやめておきますが、ぜひ機会があれば
皆さんにも一度は触れてみていただきたい音世界です。
そこらのおもしろい音のする缶とかベルとかを寄せ集めて作った妙ちきりんな楽器「ロバの脚」のダンス。新聞紙や厚紙を使った音探しのパフォーマンス。
怪しい仮面の酔っぱらい3人組による、瓶の音楽。
どれも小芝居仕立てで、子どもたちを決して飽きさせません。
子どもたちもお母さんたちも、手拍子足拍子でノリノリになったり、おなかを抱えて
大爆笑したり。心の底から音を楽しみました!
これが本当の「音楽」ってやつですね。
なおー専務も大喜びで、最後は会場を走り回り、演奏中だろうがステージを横切る!
他の子どもたちも、思い思いにからだで音楽を楽しんでいました。
こんなのっていいなぁ!
普段すっかり理屈っぽくなりがちな私たち。
音楽演っていたってそうなんだもの、
時には大人も子どもに戻って、音を自然をからだで楽しまなくちゃ!
そんな親子ですごーく豊かな気持ちになった一日でした。
帰り道、その日たった一度しか聴いていない唄を口ずさんでいたなおー専務!
子どもの感じる力って無限大かも!とあらためて感激したおまけつきでした。
2011年02月20日
キッチンスペシャリストと名乗っていいそうです
ウラ夫です。こんにちは。
昨年末、キッチンスペシャリストという認定試験を受けました。
インテリアコーディネーターという資格を認定しているとこの
キッチン版みたいなものです。
キッチンのデザインを本格的に始めて、はや7年目に入りました。
キッチンをデザイン・設計するにあたっては、これまで取り組んできた
家具のデザインや木工の知識、それに加えて、毎日家族の皿を洗い、
料理に余分な手心を加えるエセ主夫っぷりなどが、大変役に立ってきたわけですが、
実際は、毎回お会いするお客さまに教えられることも数限りなく多いのです。
ここらで一度体系的に勉強し直しておこうと思い、普段はあまり縁のない
受験勉強などしてみたわけです。
内容はキッチンや住まいの歴史から始まって、人間工学や住宅設備の知識、法律、
販売知識、マーケティング、そしてもちろん、キッチン設計の実技など、
かなり幅広いものでした。
中には、「台所」の語源が平安時代にさかのぼる、なんていう、
アタック25で勝ち抜くためのニッチな知識から、
お客さまにはきちんと「いらっしゃいませ~」と元気よくあいさつせよ的な、
新入社員はビシッとしつけろよなんていう楽しいコーナーもありつつ、
楽しく学んできました♪
そうは言っても、実際にキッチンをデザインし続けて6年。
既に100件以上のご家族と頭をつきあわせて考えてきました。
今さら落ちたら、正直何だかな~といった感じですが、無事パスできて
よかったです。
けど、今回挑戦してみてわかったことは、キッチンの専門家としてお客さまに、
そして現場で求められていることは、もっともっと深いもので、
スペシャリストとはいうものの、これはまだその序の口に立ったに過ぎない、
ということ。
キッチンを取り巻く環境は日々変わっていくし、なにより、
自分たちにぴったりのキッチンがほしい!と相談にいらして下さるお客さまが
大切にしていることは、ひとりひとりみんな違うんです。
(それがとっても楽しいし、やりがいでもあるんですが)
これから、もっと専門性をみがき続けていく必要があるぞ!と心あらたです。
だまさんが目下つわりで沈没中により、料理・子育て・家事に尽力せざるを
得ないのも、こりゃありがたい修行かも知れないよ~♪ (とムリヤリ前向き)
というわけで、これからみなさんが市中でウラ夫さんを見かけた際には、
「キッチンスペシャリストのウラ夫さんですよねっ!!」
などと、大きな声で呼んでいただくというのも可です。
繰り返しますが、得意科目は皿洗いです。
2011年02月15日
信州大付属病院の燻製たまごが異常に美味しい件
ちまっとした話題で恐縮です。
だまさんが信州大付属病院の産科に検診に行ってきました。
売店で山のように売っていたとのことで、燻製たまごを買ってきてくれました。
これが美味しい!
ゆで卵自体、あまり好んで食べる方ではなかったので、ハッキリ言って
なめてたんですが、
半熟の黄身にまで、燻製の香りと色がしみ込んでいて非常に美味しく、
飲むように食べてしまいました♪
(食べてしまってから気がついたので、上の画像はイメージです。)
うーむ、ゆで卵の分際で上等なヤツ…。
燻製たまごって、こんなに美味しいものとは知りませんでした。
完敗…。
ちなみにこの売店、他にもいかにも手作り風のタコやイカの燻製、
お惣菜、漬け物など、酒のツマミ系が妙な充実を見せているらしい。
病院だよね…?
これからしばらく足を運ぶことも多いと思うのですが、
楽しみな隠れスポット見つけました。
場所が場所だけに、皆さんもどうぞ、というわけにはいきませんが…。
2011年02月08日
友だちが農家になりました
ウラ夫です。
先日、友人のK野さんがサラリーマンをやめました。
数年前から計画してのことです。
30代半ばの彼が新しく選んだ道は農業。
K野さんは東京からこの松本にやってきた人で、農家の生まれではありません。
でも、いつかは農業をやりたい!というのが、彼の長年の夢だったんです。
そして、彼が今取り組もうとしているのは、「無肥料栽培」。
農薬はもちろん、有機肥料さえも使わない農業です。
植物は、本来自分自身で育ち、実る力を充分に持っている。
ところが、今の野菜や穀物は、肥料漬けになってしまっていて弱く、
だから農薬やより多くの肥料がないとちゃんと育たなくなってしまっているのだとか。
うーむ、野菜も現代っ子になっているということね…。
実際、肥料のやりすぎで、野菜の中にこれまであまり知られていなかった
有害物質がたまってきていると聞きます。
これは有機野菜でも同じことだそう。
K野さんは、この日本の食と農業を何とかしたい!と立ち上がりました。
この話を聞いてすぐに、σ(^^)はK野さんを知り合いの雑穀レストランに誘って、
その可能性に夢ふくらめたり、ことあるごとに、彼のビジョンを聴きました。
いや~、彼は熱い!
σ(^^)がママルのキッチンを通して世の中に創りたいこと、
「多くの家族が幸せで、人とものが支え合って生きる、心豊かな世界を創る」
に通じるものを強く感じました。
おかげで、彼とわかちあうと、夢が広がりすぎてお互い止まらない!
彼の計画を聴くと、σ(^^)もアイディアがあふれてきてしまう~♪
彼は数年前からサラリーマンを続けながら、畑の土の中に残った
「肥料を抜く」ために雑穀を作るなどして、着々と準備を進めてきました。
野菜や雑穀の直売や宅配なども始めていて、σ(^^)もお世話になっています。
旬の時に旬のものが届くという、ごく当たり前のことがうれしいんです。
こどもたちには、野菜の本当の旬とおいしさを教えてあげたくて、
夏には夏野菜、冬には冬野菜と、なるべくその時のものを食べるようにしています。
特に高キビ、モチキビ、アマランサスなどの雑穀はうれしい!
雑穀のおいしさに目覚めて、時々料理するんですが、国産無農薬の雑穀って
なかなか手に入りにくいんですよ。しかも高い。
おかげで我が家は「絶好腸」です♪
この春から、K野さんは本格的な営農に挑戦します。
若く、高い志を持った彼をこれからも応援していきます。
またことあるごとにご紹介していきたいと思います。
2011年02月05日
見学会のお知らせ!
ウラ夫です。
先日は雪の残る大町市でキッチンの設置工事でした。
建てられたのは、自然素材での家づくりの先がけ、アトリエデフさん。
画像はまだ設置途中ですが、
スギで作った、ごくシンプルなキッチンです。
素朴な木のキッチンですが、最新の食洗機がビルトイン、
引き出しレールも最高品質のものなので、毎日のストレスがありません。
さて、このお家がこのほどついに完成。
この土日に見学会が開かれます。
自然素材で、安全安心なキッチン、住まいをお考えのみなさん、
ぜひお出かけくださいね!
「大町の家」 ― 大町市 ― 完成見学会
【日にち】 2月5日(土)6日(日)
【時 間】 10:00~16:00
【場 所】 大町市
*信濃大町駅近く
*案内図はコチラ!←クリック
2011年02月02日
赤ちゃんが出来ました
ウラ夫です。
パートナーのだまさんに赤ちゃん(二人目)が出来ました。
年末からからだの具合は絶不調だったのですが、
ついこの間まで全く気がつきませんでした。
気がつくともう4ヶ月(←オイオイ)。
ずいぶん大きくなってました…。
これがつわりとわかると、胸を張って沈没できるようで(?)、
σ(^^)の主夫生活が始まりました!
(もともと家事好きなので、平気)
上の子の時の経験から、まずは環境整備。
レンジフードをクリーニングして、ガスコンロを新調(古かったので)。
キッチンからネギ・ニンニクの類を除去しました。
食事はいまのところ、農家の友人が作ってくれた無肥料野菜を、
テキトーに煮たり茹でたりしたものが主。
幸いσ(^^)も野菜好きなので、もう久しく肉を食べてませんが、
逆に体力がついてきたような気がします。
初めての子を産むまではジャンクフード大好きなだまさんだったのですが、
赤ちゃんが出来た途端、眠っていたセンサーが働き始めたのか、
いかなる食材からも、化学調味料を「にがい!」と検出するように。
それまで使っていた、ほ☆だしの類が強制的に排除され、
外食と焼きそばUF☆などがお気に入りだっただまさんが、
かつお節で全てのだしをとるようになりました。
母体の神秘です。すごいな。
今では、出来る限りの食材を生活クラブで揃えてます。
おかげで、家族そろって素材の本当のおいしさに開眼し始めた感じです。
(余談ですが、不思議とママルのキッチンを選ばれるお客さまには
生活クラブを利用されてる方が、とっても多いんです。結構な確率♪)
まぁ、それでも時々、無性にからだに刺激を与えたくなって、ケン☆ッキーとか
ため食いするんですけどね…。
さて、今晩のご飯は何にするかな~。
2011年01月26日
横引きレンジフードは安全か?
ウラ夫です。
先日、あるお客様から、横引きのレンジフードを使いたい、とのご相談を受けました。
横引きのレンジフードとは、ガスコンロやIHの正面の壁に小窓が開いていて、そこから調理の排気を勢いよく吸い込むというものです。
従来のフードのように天井からコンロを覆うようなかたちが必要ないので、調理機器の周りがすっきり納まるというのが最大の売りなのですが、詳しく調べていくと、意外な事実が判明。
それは、一言で言うと、
「横引きフードは、法規上、設置は認められていない」
ということ。
恥ずかしながら、私もこれまでは、製品として成立しているのだから、当然設置に問題はないものと考えていました。(実際の設置例はありませんが…)
ところが、事実は建築基準法や消防法の原則にかなっていないため、このタイプのフードは設置できないということになります。
その原則とは、レンジフードなどの換気設備は、加熱機器の上方80センチ以上離れた高さに設置しなければいけない、というもの。
なぜこの原則が決められているのか、最悪の事態を想定して考えてみましょう。
天ぷら鍋を加熱したまま忘れてしまい、鍋の油が発火し、炎があがったとします。
真上にあるレンジフードは不燃材で作ることになってはいますが、フードと炎の間に適切な距離が保たれていないと、フィルターや内部の油汚れなどに着火し、火災につながることが考えられます。
このような事態を避けるために、80以上センチ離しなさい、と規定しているわけです。
さて、横引きフードの場合はどうなるでしょう。
鍋から立ち上った炎は、壁面の排気口にそのまま引き込まれてしまうと考えられます。(通常使用でも、コンロの炎が排気口側にたなびくほど強力です)
本体やダクトの内部には、多少なりとも油を含んだ汚れが付着していますから、これらに着火しつつ、最悪の場合、ダクトを伝わって建物の本体にまで延焼してしまう可能性も否定できません。
恐いですね!
ちなみに、これは鍋の油から発火した場合を想定していますので、ガスでもIHでも同じ危険性があります。
ずいぶんと恐い話になってしまいましたが、キッチンは火や熱をあつかう場所である以上、安全であることを第一に考えなければいけない、ということなのです。
特に設計者や施工業者は、デザイン性を優先するあまり、法規上OKだから、とか、これなら法律の網をくぐり抜けられるから(!)、といった考え方になりがちです。
でも、本当に大切なのは、そこに住まう方が、安心して永く暮らせることであるはず。
法律がどうか、ということ以上に、より安心できる住まいをつくるために、最も大切なことを忘れず、また、常日頃からあらゆる情報を集め、検証していくことも、プロの仕事と肝に銘じていきます。
どんなに接着剤や塗料の安全に気をつけたキッチンでも、燃えてしまっては意味がないですからね~。
2011年01月21日
キッチンづくりの中で感じたことを書いていきます
ウラ夫です。

事務所移転やら何やらで、このブログもおろそかに…。
なんとも面目ありません。
気を取り直していきますので、どうぞおつきあいの程を。
さて、日々多くの方のキッチンをプランしているわけですが、
いろいろな情報に振り回されて、
あるいは、知らなかったがために、
本当に望んだキッチンにたどり着けない(たどり着けなかった)
という方に出会うことが、最近とみに増えてきました。
私がそう感じるようになっただけなのかも知れませんが。

キッチンは、家族の団らんや、安全安心な暮らし、
そして何より人生を楽しむための源になる、とても大切な場所です。
多くの方が、自分たちらしいキッチンで暮らすことで
少しでも人生が楽しくなるよう願っています。
今後このブログでは、多くの皆さんが自分のキッチンを選ばれる際に疑問に思うこと、また、知っていただきたいことなどのネタを投下していきたいと思っています。
日々いろいろなご家族にお会いしている中で感じたこと、
そして、これからキッチンを選ばれる、あるいは作られる方に、
これは知っていていただきたいと思うことなど、書いていきます。
キッチンづくりについてのご質問などもありましたら、お気軽にお尋ね下さいね。
では!
2010年11月01日
2010年10月05日
現時点で理想の家
だまです。
断捨離の著者、やましたひでこ先生のご自宅、
その名も「断捨離ハウス」にお伺いすることになりました。
もちろん、いいところは、全部真似してみたい。
と、ここで、
現時点での、理想のおうちを描いてみる。
リビングには、青々としげる、木立を望む
南向きの大きな窓。
白い城壁に、ヘリンボーン柄に組まれた床。
ウラ夫の作った、そっけない
ダイニングテーブルに椅子6つ。
壁側に、作りつけのキャビネット。
テレビとコンポとお気に入りの絵だけ置かれている。
うるさい物がない、静かな空間。
深呼吸の美味しい、部屋。
家族が誰もいないときは、
私が物をかいたり、パソコンしたり。
大勢の人に遊びにきてもらって、
大皿に持ったお料理を振舞う。
料理をつくるのは、ウラ夫(笑)
いっぱいビールをのんで、ワインをのんで
夜は大人だけで、お酒をのんで。
疲れたら、ゆっくり眠ってもらえる
ゲストルームもあったらいいな。
余計な物をおかず、常に掃除の行き届いた
気持ちよいおうち。
っていうのが、今の理想なんだけども。
現実はなかなかね。
断捨離ハウス訪問で、何かが変わるかな?
断捨離の著者、やましたひでこ先生のご自宅、
その名も「断捨離ハウス」にお伺いすることになりました。
もちろん、いいところは、全部真似してみたい。
と、ここで、
現時点での、理想のおうちを描いてみる。
リビングには、青々としげる、木立を望む
南向きの大きな窓。
白い城壁に、ヘリンボーン柄に組まれた床。
ウラ夫の作った、そっけない
ダイニングテーブルに椅子6つ。
壁側に、作りつけのキャビネット。
テレビとコンポとお気に入りの絵だけ置かれている。
うるさい物がない、静かな空間。
深呼吸の美味しい、部屋。
家族が誰もいないときは、
私が物をかいたり、パソコンしたり。
大勢の人に遊びにきてもらって、
大皿に持ったお料理を振舞う。
料理をつくるのは、ウラ夫(笑)
いっぱいビールをのんで、ワインをのんで
夜は大人だけで、お酒をのんで。
疲れたら、ゆっくり眠ってもらえる
ゲストルームもあったらいいな。
余計な物をおかず、常に掃除の行き届いた
気持ちよいおうち。
っていうのが、今の理想なんだけども。
現実はなかなかね。
断捨離ハウス訪問で、何かが変わるかな?
2010年10月05日
断捨離の影響
だまです。
長野県では初めての断捨離セミナー@松本。
おかげさまで早くも満席となりました。
先日、信毎(信濃毎日新聞・長野県の主要紙)で紹介されてて
テレビでは「いいとも」でも、紹介されたとか…。
そして、なんと今月号のananは断捨離特集!
まだ読んでないんだけど、
どんな内容なのかなぁ…。。。
いきなりメディアで活発にとりあげられ、
個人的な思いで主催した松本セミナーにも
大勢の注目が集まり、
なぜか、ちょっと、緊張…。
お申込みの皆さんと、メールのやりとりしてると
皆さん、元気でおもしろくて、早く会いたくなる♪
楽しみだなぁ…。
長野県では初めての断捨離セミナー@松本。
おかげさまで早くも満席となりました。
先日、信毎(信濃毎日新聞・長野県の主要紙)で紹介されてて
テレビでは「いいとも」でも、紹介されたとか…。
そして、なんと今月号のananは断捨離特集!
まだ読んでないんだけど、
どんな内容なのかなぁ…。。。
いきなりメディアで活発にとりあげられ、
個人的な思いで主催した松本セミナーにも
大勢の注目が集まり、
なぜか、ちょっと、緊張…。
お申込みの皆さんと、メールのやりとりしてると
皆さん、元気でおもしろくて、早く会いたくなる♪
楽しみだなぁ…。